高血圧とは?|岡山市南区にじいろ内科・小児科クリニック
高血圧とは?|岡山市南区にじいろ内科・小児科クリニック
高血圧とは「血管の中を流れる血液の圧力が強くなり続けている状態」であり、長時間続くと動脈硬化を引き起こします。なぜ高血圧が起こって、どうして高血圧だとよくないのでしょうか?血圧の基本と基準値について
血圧とは、心臓が血液を全身に送り出すときに血管の壁へかかる圧力のことです。この血圧は一日を通して変動しており、朝の目覚めや運動、寒さ、緊張などによって一時的に上昇します。高血圧とは、こうした一時的な上昇ではなく、安静時にも血圧が慢性的に高い状態が続くことを指します。 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」では、測定環境にもよりますが、診察室で計測した場合の血圧は、最高血圧で140mmHg以上、最低血圧90mmHg以上が基準とされています。 例えば、診察室で140/90mmHg以上が繰り返し記録される場合、「高血圧症」と診断されます。 血圧は、- 心臓が血液を押し出す力(心拍出量)
- 血管の抵抗(血管の硬さや収縮)
日本人に高血圧が多い理由
日本では、成人の約3人に1人(約4,300万人)が高血圧といわれています。 そのうち、血圧を適正にコントロールできている人はわずか27%程度にとどまっています(厚生労働省「国民健康・栄養調査2022」より)。 特に日本人に高血圧が多い理由として、以下の3つが挙げられます。-
食文化の影響(塩分過多)
味噌、しょうゆ、漬物などの塩分を多く含む食品を日常的に摂取。 日本人の塩分摂取量は欧米人の約1.5倍といわれています。 -
気候の影響(寒暖差による血圧上昇)
冬の寒さで血管が収縮し、血圧が上がりやすい。 岡山市南区など内陸地域では、特に朝晩の冷え込みに注意が必要です。 -
自覚症状の乏しさによる放置
高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれ、頭痛・めまい・肩こりなど軽度な症状しか出ないことも多いため、受診が遅れがちです。
- 「高血圧と知っているが治療を受けていない」人は約450万人(全体の11%)
- 「高血圧に気づいていない」人は約1,400万人(全体の33%)
高血圧の主な原因|岡山市南区にじいろ内科・小児科クリニック
高血圧の約90%は「本態性高血圧」と呼ばれ、はっきりとした病気が原因ではなく、生活習慣や遺伝など複数の要因が重なって発症しています。本態性高血圧を除いたおよそ10%は、腎臓の病気や内分泌異常、睡眠時無呼吸症候群などによる「二次性高血圧」です。この場合は、原因を特定して治療することにより血圧を効果的に下げることができるため、適切な診断が重要になります。特に、30歳未満の高血圧、急激な高血圧、薬をたくさん飲んでもよくならない高血圧には二次性高血圧が疑われます。その場合は早めにかかりつけ医を受診しましょう。よくある高血圧の主な原因として、国立循環器病研究センター(参考はこちら)および日本高血圧学会(参考はこちら)は以下を挙げています。高血圧になる原因①:塩分の摂りすぎ
塩分を多く摂ると体内に水分がたまり、血液量が増加して血圧が上がる。日本人の平均塩分摂取量は1日10.1g(目標は6g未満)と過剰傾向。高血圧になる原因②:肥満
BMI25以上では血管への負担が増え、動脈硬化を促進。体重を5kg減らすと平均で収縮期血圧が4〜5mmHg低下。高血圧になる原因③:運動不足
運動を週3回以上行うと血管の柔軟性が改善し、血圧を約5〜8mmHg下げる効果がある。高血圧になる原因④:飲酒・喫煙
飲酒量が1日アルコール30mlを超えると血圧上昇。喫煙は交感神経を刺激し、一時的に20mmHg以上血圧を上げることも。高血圧になる原因④:ストレス・睡眠不足
自律神経の乱れにより血管が収縮。慢性化すると持続的な高血圧を招く。近年高血圧が増えている原因とは?|岡山市南区にじいろ内科・小児科クリニック
食事や生活習慣の影響
日本人の平均食塩摂取量は1日10.1g(厚生労働省「令和4年国民健康・栄養調査」)で、日本高血圧学会が推奨する男性7.5g未満・女性6.5g未満を大きく上回っています。
塩分を摂りすぎると体に水分がたまり、血液量が増加して血圧が上がります。研究では、塩分摂取を6g/日に減らすことで、平均4〜5mmHgの血圧低下が見られたと報告されています。
また、肥満も重要なリスク要因です。体重を5kg減らすと、収縮期血圧が約4〜5mmHg低下することが知られています。岡山市南区のように車移動が中心の地域では、「買い物のとき1駅分歩く」「エレベーターより階段を使う」といった日常の工夫が効果的です。
過度な飲酒や喫煙も血圧を上げます。アルコールを1日30mL(日本酒1合)以上摂取すると血圧が上昇し、喫煙直後は交感神経の刺激で一時的に20mmHg以上上がることもあります。これらの習慣を見直すことで、薬を使わなくても血圧が安定するケースも少なくありません。
遺伝や体質によるもの
高血圧は遺伝の影響も大きく、親が高血圧の場合、子どもが高血圧になるリスクは約2倍に上がると報告されています。
また、加齢による血管の硬化も避けられません。動脈の弾力が失われると血流の抵抗が増し、自然と血圧が上がります。女性では更年期以降、エストロゲンの減少により血圧が上がりやすく、男性では40代以降に動脈硬化が進行して高血圧が顕著になります。
遺伝的体質を完全に変えることはできませんが、「遺伝+生活習慣」=発症リスクという点を意識し、塩分・体重・睡眠・運動を意識的に管理することで予防が可能です。
ストレスや睡眠不足の関係
ストレスを感じると、自律神経のうち「交感神経」が活発になり、血管が収縮して血圧が上がります。慢性的なストレスや睡眠不足は、日常的な高血圧を引き起こす原因となります。
日本高血圧学会は、1日7時間前後の睡眠を目安にするよう推奨しています。また、定期的な休養や軽い運動(ウォーキング・深呼吸など)には、血管を拡張しストレスホルモンを減らす効果があります。岡山市南区では、旭川沿いや浦安総合公園周辺など、自然の多い環境を活かした軽い運動や気分転換がおすすめです。
※このセクションは以下のエビデンスを基にしています:
-
日本高血圧学会『高血圧治療ガイドライン2019』
-
国立循環器病研究センター「高血圧について」
-
厚生労働省『令和4年国民健康・栄養調査』
-
Fujiyoshi A. et al., Hypertens Res, 2012
高血圧の症状と注意点|岡山市南区にじいろ内科・小児科クリニック
血圧の症状
高血圧が進行すると、血管壁の弾力性やしなやかさが失われます。 さらに、血管壁に傷ができてしまうことでコレステロールなどが沈着すると、動脈硬化がより進行し、血管内が細くなってしまい、狭い血管内に血液を流すためにさらに血圧が高くなります。 また、心臓、脳、大動脈、腎臓など、さまざまな臓器に負荷をかけてしまいます。特に日本人では、脳梗塞や脳出血を発症する人が欧米人に比べて多いといわれており、血圧のコントロールはとても大切です。 高血圧は、目立った症状が少なく自覚症状のないままに徐々に進行していきます。そのため健康診断で初めて指摘されることが多いようです。 日本の高血圧患者は、全体として約4,300万人いると推定されており、日本人のおよそ3人に1人が高血圧という状況です。食生活の欧米化や人口の高齢化に伴い、今後も増加すると考えられています。もはや国民病であり、早期診断早期治療することが重要です。自覚症状が少ない理由
高血圧は、初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。血圧が高くても痛みや不快感がないため、放置されがちです。
そのため、高血圧は「サイレントキラー(沈黙の殺人者)」と呼ばれています。
脳や心臓、腎臓などの臓器は、血管が少しずつ傷ついてもすぐには症状が出ません。
血管へのダメージが長期間続いた結果、突然の脳卒中や心筋梗塞として現れることがあります。
日常でみられる軽度のサインとしては、
-
朝の頭痛や重だるさ
-
めまい・耳鳴り
-
肩こり・動悸
-
顔のほてり
などがありますが、これらはストレスや疲労と区別がつきにくいため、自己判断では見逃されやすいのです。
放置すると起こる合併症
血圧が高い状態が続くと、血管の内壁が傷つき、動脈硬化が進行します。その結果、次のような重大な合併症を引き起こす危険性があります。
| 高血圧を放置することで起こる合併症 | |
|---|---|
| 合併症 | 主な症状・影響 |
| 脳卒中(脳出血・脳梗塞) | 突然の意識障害・手足の麻痺・言葉が出にくい |
| 心筋梗塞・心不全 | 胸の痛み・息切れ・疲れやすさ |
| 慢性腎臓病(CKD) | むくみ・だるさ・尿量の変化 |
| 網膜症(眼底出血) | 視力低下・かすみ・失明の危険 |
早めの受診が大切な理由
高血圧は「治療よりも早期発見と継続管理」が重要な病気です。日本高血圧学会では、40歳を過ぎたら年1回の健診+家庭血圧の定期測定を推奨しています。にじいろ内科・小児科クリニック(岡山市南区)では、
-
診察室と家庭での血圧差(白衣高血圧・仮面高血圧)の評価
-
血液・尿・心電図・エコーによる臓器ダメージのチェック
-
管理栄養士による食事・減塩指導
などを組み合わせ、原因と状態に合わせた診療を行っています。
「症状がない=問題がない」ではありません。たとえ血圧が少し高い程度でも、早めの受診が将来の合併症予防につながります。
高血圧の検査と診断の流れ|岡山市南区にじいろ内科・小児科クリニック
高血圧は基本的に、血圧測定が主な検査です。高血圧の診断では、「どのくらい血圧が高いのか」「なぜ上がっているのか」を正確に調べることが大切です。岡山市南区のにじいろ内科・小児科クリニックでは、単に血圧を測るだけでなく、生活習慣・体質・臓器の状態を総合的に評価し、一人ひとりに合わせた診断を行っています。血圧測定(診察室と家庭血圧)
高血圧の診断は、1回の測定値では決まりません。診察室での測定(診察室血圧)に加え、自宅での測定(家庭血圧)を組み合わせることで、より正確な診断が可能になります。 一般的には、診察室血圧と家庭血圧が診断に用いられます。最近の医学的な研究により、心筋梗塞や脳卒中の発症を予測する方法として、診察室血圧よりも家庭血圧の方が、信頼性が高いことが分かってきました。高血圧学会のガイドラインでも、高血圧の判定では、家庭血圧にもとづくほうを優先するとしています。 高血圧であるか、あるいはどのくらいのレベルに分類されるかは、次のように定められています。| 分類 | 診察室で測定した時(mmHg) | 自宅で測定した時(mmHg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | |||
| 正常血圧 | <120 | かつ | <80 | <115 | かつ | <75 |
| 正常高値血圧 | 120-129 | かつ | <80 | 115-124 | かつ | <75 |
| 高値血圧 | 130-139 | かつ/または | 80-89 | 125-134 | かつ/または | 75-84 |
| 高血圧 | 140以上 | かつ/または | 90以上 | 135以上 | かつ/または | 85以上 |
血液・尿・心電図・エコーなどの検査
血圧が高い原因や、臓器への影響を調べるために、以下のような検査を行います。
| 検査内容 | 確認できること |
|---|---|
| 血液検査 | 腎機能(クレアチニン)、コレステロール、血糖値などをチェックし、生活習慣病との関連を評価。 |
| 尿検査 | 尿中のタンパク・ナトリウムなどを測定し、腎臓への負担を確認。 |
| 心電図・心エコー | 心肥大・不整脈・心筋の状態を調べ、心臓への影響を評価。 |
| 頸動脈エコー | 動脈硬化の進行度を画像で確認。 |
| 必要に応じてホルモン検査 | 原発性アルドステロン症など、二次性高血圧の有無をチェック。 |
にじいろ内科・小児科クリニックでは、血圧の数字の背景にある「体のサイン」を見逃さないことを重視しています。生活習慣の問題だけでなく、腎臓やホルモンの異常が疑われる場合は、早期に専門的な追加検査へ進みます。
高血圧のタイプを見極める
一口に「高血圧」といっても、そのタイプによって対処法は異なります。当院では、以下のように患者さんの状態を分類し、最適な治療方針を立てています。
| タイプ | 特徴 | 主な対応 |
|---|---|---|
| 本態性高血圧 | 生活習慣・体質が関係する一般的な高血圧 | 食事・運動・薬物療法の組み合わせ |
| 二次性高血圧 | 腎臓・ホルモン異常など特定の病気が原因 | 原因疾患の治療(腎・内分泌評価) |
| 白衣高血圧 | 医療機関でだけ血圧が高くなる | 家庭血圧を重視し、経過観察 |
| 仮面高血圧 | 家庭では高いが診察室では正常 | 生活習慣改善+家庭血圧管理 |
このように、「なぜ上がっているのか」まで丁寧に調べることが、的確な治療の第一歩です。
当院が推奨する高血圧の治療方法|岡山市南区にじいろ内科・小児科クリニック
ここでは本態性高血圧の治療を中心に説明させていただきます。いくつかの治療方針がありますが、患者さまご自身が治療に前向きになり、継続していくことが重要です。非薬物療法
すぐにでも始められる方法として、非薬物療法があります。 具体的には、減塩、体重の減量、適度な運動、アルコールの摂取量を減らす、食事内容の改善があげられます。特に食塩は、腎臓の働きの一部を障害し、血液の量を増やしてしまいます。すると血圧がさらに高くなり心臓に負担を与えることになるため、高血圧には減塩が必要です。さらに食塩による血圧は、男性よりも女性の方が上がりやすく、若い人よりも高齢者の方が上がりやすいといわれています。 健康な日本人が当面目標とすべき1日の食塩摂取量は、男性で8g未満、女性で7g未満とされています。しかし実際の食塩摂取量の平均値は9.9gであり、男女別にみると男性10.8g、女性9.1g、平均2g程度上回っている状況です。既に高血圧となっている方では、1日6g未満を目指すと良いでしょう。 また、肥満や過度の飲酒も、高血圧の原因となることが分かっています。腹八分目を意識し、過食を防ぐためにも週一回以上は体重を確認し、飲酒習慣のある方は週一日以上の休肝日を設けるようにしましょう。 心臓や脳など他の部位に病気がなければ、ウォーキングなどの有酸素運動を毎日30分以上行うのも有効です。野菜や果物には、血圧を下げる働きのあるカリウムが多く含まれる食品があります。バランスの良い食事を心がけましょう。 また喫煙は血管が収縮し、一時的に血圧が上がります。喫煙により血液の流れを悪くし、血液が凝固しやすくなるため、動脈硬化の最も強力な危険因子です。 これらの生活習慣は、複合的に改善を行うことがより効果的です。食習慣の乱れや食事の偏りを少しでも改めることで、高血圧の治療だけでなく、生活習慣病の予防にも結び付けることができます。薬物療法
充分な生活習慣の改善を行っても、血圧のコントロールが不十分である場合は、降圧薬治療が必要になります。降圧薬にはいくつか種類がありますが、よく使われるものは下記の4種類になります。- カルシウム拮抗薬:血管を広げて血圧を下げる
- レニン-アンジオテンシン系阻害薬(ARB、ACE阻害薬):血管を収縮させる体内の物質をブロックして血圧を下げる
- 利尿薬:血液から食塩と水分(血液量)を抜いて血圧を下げる
- β(ベータ)遮断薬:心臓の過剰な働きを抑えて血圧を下げる
高血圧に関してよくある質問|岡山市南区にじいろ内科・小児科クリニック
Q1. 薬は一度始めたら一生続けないといけませんか?
A. いいえ、必ずしも一生続けるわけではありません。
にじいろ内科・小児科クリニックでは、「減薬・中止を見据えた治療」を大切にしています。
生活習慣を改善し、血圧が安定した状態が続けば、医師の判断のもとで薬の量を減らしたり、中止することも可能です。
ただし、自己判断で中止すると血圧が急上昇するリバウンド現象が起こることがあります。
当院では家庭血圧データをもとに経過を丁寧に追い、「薬を減らしても安心できる状態」を確認しながら調整します。
Q2. 家庭血圧と病院の血圧、どちらを重視すべきですか?
A. どちらも大切ですが、当院では「家庭血圧」をより重視しています。
診察室では緊張によって血圧が高くなる「白衣高血圧」や、逆に家庭では高い「仮面高血圧」など、環境による差が生じるためです。
家庭血圧は、朝起きて1時間以内・夜寝る前など、リラックスした状態で測定することで、より“本来の血圧”がわかります。
当院では、患者様にご自宅で測定していただいたデータを共有してもらい、その数値を治療方針に反映しています。スマートフォン連携型の血圧計(オムロン製など)の使用方法も丁寧にサポートしています。
Q3. 減塩ってどのくらいが目安ですか?
A. 日本高血圧学会では、1日6g未満の食塩摂取を推奨しています。
ただ、普段の食事でどのくらい塩を使っているかを正確に把握するのは難しいものです。
にじいろ内科・小児科クリニックでは、
管理栄養士が日常の食事内容を一緒に確認し、
「無理なく続けられる減塩」を提案します。
たとえば、
-
出汁・酢・レモン汁・スパイスで“味の深み”を出す
-
味噌汁は1日1杯までにする
-
醤油は「かける」より「つける」
-
漬物・加工食品は控えめに
など、具体的な方法をわかりやすくお伝えしています。
Q4. 血圧が高いとき、すぐに受診したほうがいいの?
A. はい、180/110mmHg以上のように非常に高い場合や、頭痛・めまい・息苦しさ・胸の圧迫感などの症状を伴う場合は、すぐに受診してください。
一方、140〜160mmHg程度であっても、数日続くようなら早めにご相談ください。当院では、血圧の変化が一時的か慢性的かを見極め、必要に応じて血液検査・心電図・エコーなどを行います。
「少し高めかな?」という段階での受診が、脳卒中や心臓病を防ぐ最善のタイミングです。
Q5. 高血圧の薬を飲んでいても、お酒や運動はしていいですか?
A. どちらも適度であれば大丈夫です。
運動は、ウォーキングなど軽い有酸素運動を週3〜5回行うことで、
平均で収縮期血圧を5〜8mmHg下げる効果があります。
激しい筋トレや無理なランニングは、かえって血圧を上げるため注意が必要です。
お酒は1日アルコール20〜30mL(日本酒1合・ビール中瓶1本程度)までが目安です。
過剰な飲酒は薬の効果を弱めることもありますので、量を守りましょう。
Q6. 高血圧は治る病気ですか?
A. 完全に「治る」というよりも、コントロールできる病気です。
高血圧は生活習慣と深く関係しているため、原因を取り除き、血管や臓器への負担を減らすことで健康を維持できます。
にじいろ内科・小児科クリニックでは、「薬を増やす」のではなく、生活を整え、将来的に薬を減らせる状態を目指しています。
患者さん一人ひとりの体質・生活・意欲に寄り添いながら、無理のないペースで改善していけるようサポートいたします。
【執筆者】内科医師 今井 佑輔
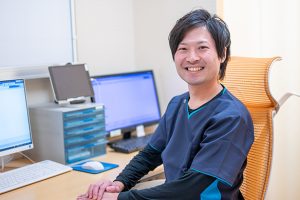
専門資格
- 医師
所属学会
- 日本内科学会
- 日本糖尿病学会




