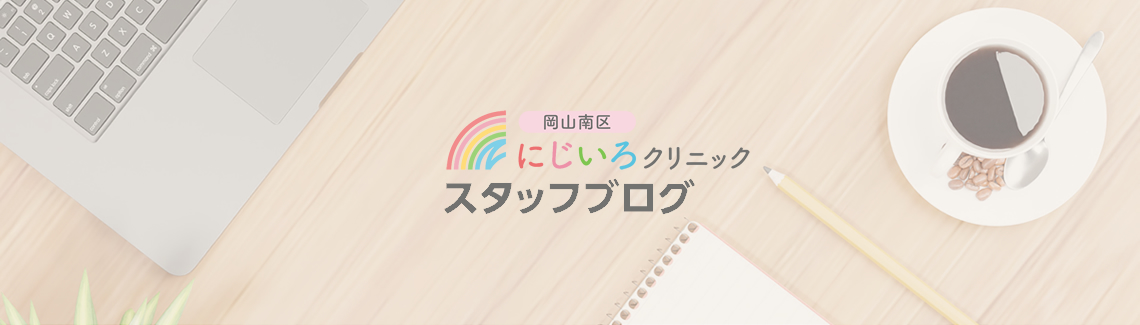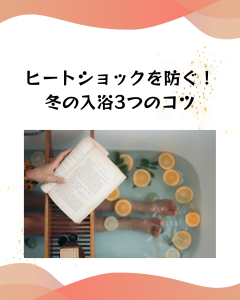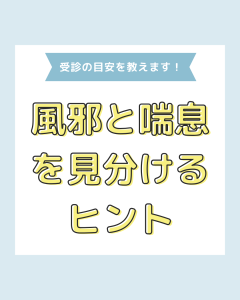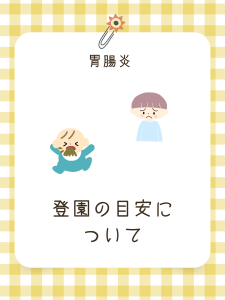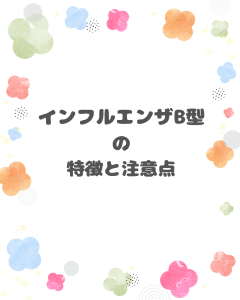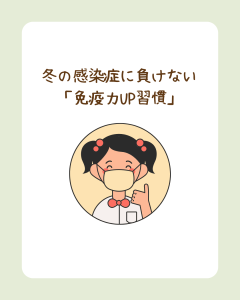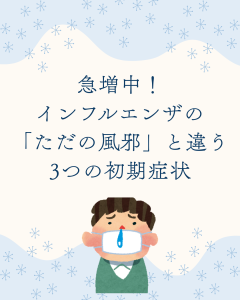「急に吐き気がして、水さえ飲むのがつらい…」そんな経験はありませんか?特に岡山市南区にお住まいの働き盛りの世代や、家事に追われる世代の方は、少々の体調不良では無理をしてしまいがちです。しかし、吐き気が続くときに最も怖いのは「脱水症状」です。体内の水分や塩分が失われると、回復が遅れるだけでなく、重症化するリスクもあります。今回は、家庭でできる正しい水分の摂り方と、受診の目安についてお伝えします。
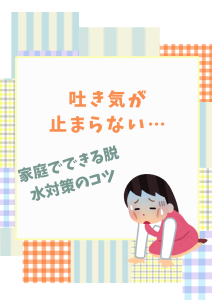
1. なぜ「吐き気」のときは水だけを飲んではいけないのか?
吐き気が強いとき、つい「とりあえずお水かお茶を」と手に取りがちですが、実はこれには注意が必要です。嘔吐によって失われているのは、水分だけではなく「ナトリウム(塩分)」や「カリウム」といった電解質も同時に失われています。
真水ばかりを飲んでしまうと、血液中の塩分濃度がさらに薄まり、脳が「これ以上濃度を下げないために、水分を排出しよう」と指令を出してしまいます。これを「自発的脱水」と呼び、飲んでいるのに脱水が進むという悪循環に陥るのです。岡山市内でもドラッグストアなどで手軽に手に入る「経口補水液(OS-1など)」が推奨されるのは、体液に近いバランスで効率よく吸収されるためです。
2. 吐き気が強いときの「ちびちび飲み」のススメ
「吐き気があるけれど、何か飲まなきゃ」と焦って、コップ一杯をグイッと飲んでいませんか?胃が敏感になっているときに一度に大量の水分を入れると、その刺激で再び嘔吐を誘発してしまいます。
家庭で実践していただきたいのが「スプーン1杯からの保水」です。
-
まずは5分おきに、ティースプーン1杯(約5ml)の経口補水液を口に含みます。
-
それで吐かなければ、少しずつ量を増やしていきます。
「たったこれだけで足りるの?」と不安になるかもしれませんが、吐かずに吸収させることが最優先です。特に岡山市南区の夏場や乾燥する冬場は、室内でも水分が失われやすいため、この「ちびちび飲み」を根気よく続けることが回復への近道となります。
3. 岡山市南区の生活に潜む、脱水を悪化させる意外な習慣
当院に来院される患者様のお話を伺っていると、体調が悪いときほど「栄養をつけなきゃ」と、無理に食事を摂ろうとしたり、スポーツドリンクを薄めずに大量に飲んだりする方がいらっしゃいます。
市販のスポーツドリンクは糖分が高く、吐き気が強いときには胃腸の負担になったり、下痢を助長したりすることがあります。また、「地元のおいしい果物なら食べられるかも」と桃やブドウをたくさん召し上がるのも素敵ですが、胃腸炎の初期段階では糖分が刺激になることも。まずは胃を休め、水分と電解質の補給に専念しましょう。地域柄、車移動が多いエリアですので、具合が悪い中での運転は脱水による集中力低下も招き危険です。早めの対処を心がけましょう。
4. 「これって救急?」迷った時のチェックリストと受診のタイミング
「これくらいで病院に行っていいのかな?」と遠慮される方は多いですが、脱水は進行すると点滴が必要になります。特に以下の症状がある場合は、我慢せずに当院や近隣の医療機関を受診してください。
-
おしっこの量が極端に少ない、色が濃い(半日以上出ていない場合は危険です)
-
口の中がカラカラに乾き、舌が白くなっている
-
立ち上がろうとするとフラフラする、めまいがする
-
目がくぼんできた、皮膚に張りがない
これらは体が「もう限界」と出しているサインです。30代〜60代の方は「まだ若いから大丈夫」と過信しがちですが、脱水から腎機能障害などを引き起こすケースもあります。早めの受診が、結果として最も早く仕事や家事に復帰できる方法です。
5. 吐き気が落ち着いてからの「胃腸にやさしい」復帰ステップ
少しずつ吐き気が治まってきたら、次は食事の再開です。ここでいきなり普段通りの食事に戻すと、再び胃を痛めてしまうことがあります。
おすすめのステップは以下の通りです。
-
まずは常温の経口補水液やお湯
-
次に「重湯」や「具のないスープ」
-
少しずつ「柔らかく炊いたおかゆ」や「煮込みうどん」
岡山市南区周辺には新鮮な食材が豊富ですが、回復期は脂っこいものや刺激物は控えましょう。また、吐き気が止まっても、数日は消化能力が落ちています。「お腹が空いた」と感じるまで、胃をゆっくり休ませてあげることが大切です。無理をしてぶり返さないよう、ご自身の体と対話しながら進めていきましょう。
まとめ
吐き気がある時の脱水対策は、「何を飲むか」と「どう飲むか」が運命を分けます。真水ではなく経口補水液を、焦らずスプーン1杯から試してみてください。
「にじいろクリニック」は、岡山市南区の皆様の心強い味方でありたいと考えています。少しでも不安を感じたり、ご家庭でのケアに限界を感じたりしたときは、どうぞお気軽にご相談ください。地域のかかりつけ医として、あなたの健康を全力でサポートいたします。