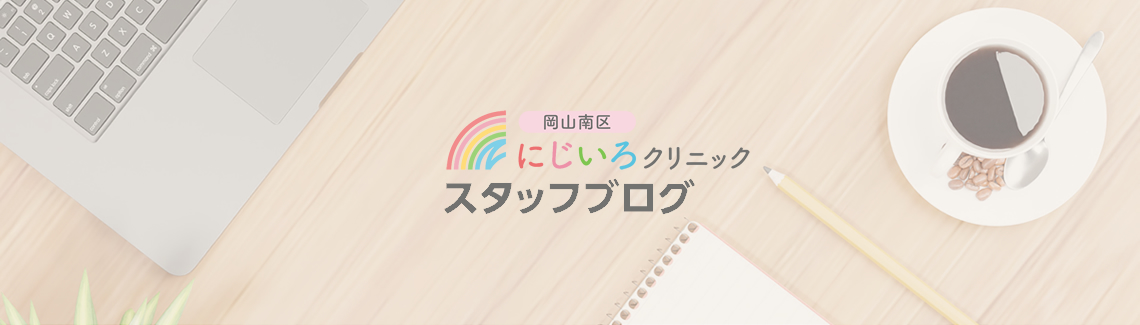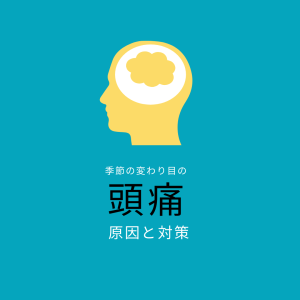今、当院で発熱で受診されるお子さまの中でインフルエンザの診断を受ける患者さまが増加傾向です。
季節の変わり目や冬本番に流行がみられる疾患ですが、予防のワクチンもまだ開始されていない季節外れのインフルエンザの流行は心配ですよね。
「もしかしてインフルエンザかも…?」と思う急な高熱、ぐったりした様子、節々の痛みなどで見るからにつらそうな子どもの姿に、どうしてあげたらいいかわからず、不安でいっぱいになりますよね。
特に、周りの保育園や学校でインフルエンザが流行していると、なおさら「うちの子もかな?」と不安になってしまうことでしょう。発熱してすぐに病院に行くべきか、それとも少し様子を見るべきか。この記事では、そんな時に役立つ「インフルエンザの受診判断ポイント」を、小児科医の視点からわかりやすくお伝えします。
症状から見分ける!インフルエンザの初期サインとは?
「高熱が出たらすぐにインフルエンザ!」と決めつける前に、まずは症状を冷静に観察してみましょう。インフルエンザの初期症状は、風邪とは少し異なる特徴があります。
風邪はのどの痛みや鼻水、くしゃみから徐々に始まることが多いですが、インフルエンザは突然38℃以上の高熱が出て、寒気や全身の倦怠感、関節痛、筋肉痛を伴うのが典型的です。小さなお子さんの場合は、これらの症状を言葉でうまく伝えられないため、「いつもより機嫌が悪い」「ぐったりして食欲がない」といった様子で気づくことが多いでしょう。また、嘔吐や下痢といった消化器症状が見られることもあります。
周りでインフルエンザが流行しているかどうかも重要な判断材料です。もし、お子さんの通う園や学校で複数の感染者が出ている場合は、インフルエンザの可能性が高いと考えられます。まずは落ち着いて、お子さんの症状と周囲の状況を合わせて確認してみてください。
検査はいつ受けるべき?インフルエンザ検査のベストタイミング
「すぐにでも検査して、はっきりさせたい!」そう思うのが親心ですよね。しかし、発熱してすぐのタイミングでは、インフルエンザの検査をしても正確な結果が出ないことがあります。
インフルエンザの検査は、鼻の奥の粘液を採取してウイルスがいるかどうかを調べる「迅速抗原検査」が主流です。この検査は、体内のウイルス量がある程度増えていないと陽性になりにくいという特性があります。一般的に、発熱してから12時間〜48時間以内が最も正確な検査結果を得られるとされています。発熱後すぐに来院された場合、陰性であっても翌日には陽性になる可能性があるため、お子さんの状態と相談しながら、検査のタイミングを判断することが大切です。
ただし、ぐったりしている、水分が全く摂れない、痙攣(けいれん)を起こした、呼びかけへの反応が鈍いなど、お子さんの全身状態が悪い場合は、時間に関わらずすぐに受診してください。
重症化が心配…すぐに病院に行くべき危険なサイン
インフルエンザは、特に小さなお子さんがかかると、肺炎やインフルエンザ脳症といった重い合併症を引き起こすことがあります。次のようないつもと違う様子が見られた場合は、様子を見ずにすぐに受診してください。
意識がはっきりしない、呼びかけに反応しない、うわごとを言う
ぐったりしていて、水分がほとんど摂れない
呼吸が苦しそう、肩で息をしている
顔色が悪い、唇が紫色になっている
痙攣(けいれん)を起こした
繰り返しの嘔吐や下痢が続き、脱水症状がみられる
これらの症状は、お子さんの体が助けを求めているサインです。夜間や休日でも、救急医療機関を利用するなどして、ためらわずに受診してください。いざという時のために、かかりつけ医の休診日や夜間・休日の連絡先を控えておくと安心です。
自宅でできるケアと注意点
インフルエンザの診断がついたら、病院でもらったお薬を指示通りに服用しつつ、自宅でのケアも大切です。
水分補給をこまめに
高熱が続くと脱水になりやすいので、こまめな水分補給が最も重要です。一度にたくさん飲ませるのではなく、スプーン1杯ずつなど、少しずつ頻回に飲ませてあげましょう。経口補水液や薄めたスポーツドリンク、果汁などがおすすめです。
しっかり休ませる
高熱がある間は無理に食べさせず、とにかく安静にして体を休ませてあげてください。消化の良いものを少しずつ摂り、エネルギーを補給しましょう。
室内の環境を整える
加湿器などを使い、湿度を50~60%に保つと良いでしょう。こまめに換気も行い、部屋の空気を入れ替えることも大切です。
解熱剤の適切な使用
熱のせいで眠れない、食事が摂れないなど、つらそうにしている場合に解熱剤を使いましょう。ただし、使用間隔は必ず6時間以上あけ、医師の指示を守ってください。
登園・登校はいつから?判断の目安について
インフルエンザは感染力が非常に強いため、学校保健安全法に基づき、出席停止期間が定められています。
「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日(未就学児)または2日(小学生以上)を経過するまで」
この2つの条件をどちらも満たしてから登園・登校が可能となります。例えば、月曜日に発熱(発症)し、水曜日に解熱した場合でも、発症から5日を経過した土曜日までは休む必要があります。また、熱が下がっても、元気がない、食欲がないなど、本調子でない場合は、無理せずにもう少し自宅で様子を見るようにしましょう。
登園・登校を再開する際は、必ず医師が記入する「治癒証明書」や保護者が記入する「登園許可書」が必要となる場合が多いので、園や学校の指示に従って準備してください。
まとめ
インフルエンザの急な発熱は、保護者の方にとって非常に不安な出来事です。しかし、まずは落ち着いてお子さんの症状をよく観察し、受診のタイミングや自宅でのケアを適切に行うことが大切です。
岡山市南区にお住まいの子育て世代の皆様が安心して育児に取り組めるよう、私たち「にじいろクリニック」はいつも皆さまのそばにいます。少しでも「あれ?」と感じることがあれば、一人で悩まず、いつでもお気軽にご相談ください。